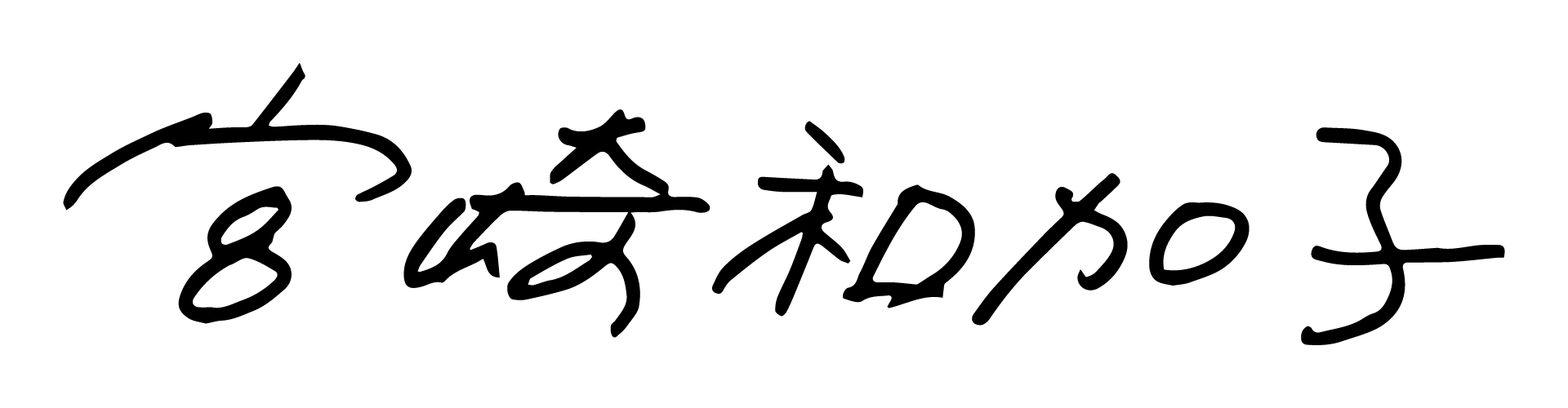『複合型サービス』の誤解
『複合型サービス』の誤解 2013年5月5日分
『複合型サービス』について考えたり見学に行ったりする機会が多いこの頃です。つい先日も実践している複合型サービスを見学に行ってきました。そこで「ええっ、複合型サービスをそういうふうにとらえていたのですか」ということがあったのでお伝えします。
「小規模多機能」と「訪問看護」がいっしょになったサービスの意味
ご存じのとおり、複合型サービスは、小規模多機能サービスの3つの機能である「通い」「泊り」「自宅への訪問(介護職の)」に、新たに『訪問看護』の機能を付け加えたサービスです。そしてこのサービスの目的は、“医療ニーズの高い要介護者への支援の充実”です。
ですから、「小規模多機能」の機能に「訪問看護」を加えたことで、医療ニーズの高い要介護者(がんの末期の方、人工呼吸器や経管栄養など医療器具を装着した状態で生活している方など)が、在宅療養生活が継続できるようにするサービスです。
「認知症」に関係なく利用が可能
ところが、「小規模多機能サービスは、認知症の人が想定されているサービスなので、複合型サービスは認知症の人で医療ニーズの高い人が対象となるのですよね」という理解をされている人がいるようです。
この制度の主旨は、認知症に関係なく、医療ニーズの高い要介護者でも利用できるサービスということです。もちろん医療ニーズが少ない方の利用も可能です。「認知症」であってもなくてもOKです。
誤解されていれば、複合型サービスは浸透しない
複合型サービスは、この一年で全国で約50か所開設されました。しかしその開設のスピードは遅い状況です。その理由はいくつもあると推測されますが、対象者を「認知症+医療ニーズのある要介護者」と誤解していることもその一因ではないかと思いました。
行政の方、事業者の方、どうぞ誤解のないように!